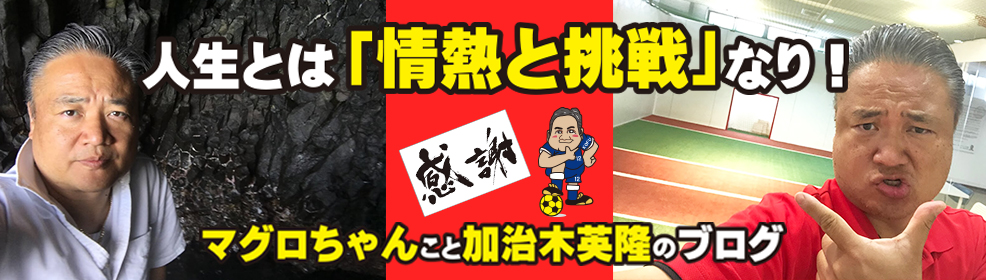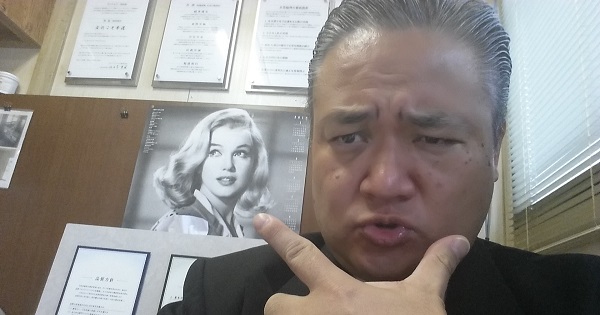チームに蔓延する当事者意識が未来をつくる。
注目の「大阪都構想」を問う住民投票の結果は賛成が694,844票(49.6%)、反対が705,585票(50.4%)という僅差でした。
ちなみに投票率は66.8%で、まぁ投票結果のコメントは避けるとして、その投票率の高さは評価できますよね。
おはようございます。
情熱と挑戦、マグロちゃんこと加治木英隆のブログへようこそ!
ブログにお立ち寄り頂き、ありがとうございます。ご縁に感謝です。
最近の政治について、なにか他人事のような雰囲気が蔓延しているように感じています。
誰かがやってくれる、自分が頑張っても頑張らなくても何も変わらない、別に政治には何も期待していない、とりあえず自分には関係ない、そんな無関心かつ他人事意識が蔓延しているように感じませんか?
実は我々の生活に一番密接に関係しているのに、ですよね。
日本の将来を考えた時、少子化問題だとか安全保障の問題だとか山積してますけど、実は「他人事意識」が一番の問題だと思いますよね。
そういった中で行われた「大阪都構想」の投票率の高さは評価出来ると思います。ちょっと安堵感、ですね。
日本の将来を考えた施策もさることながら、やはり国民一人ひとりが政治に関心を持つ、興味を持つ、これは大切な原点だと思います。
だから、一石を投じた「大阪都構想」は今後我々の政治に対してもっとコミットするきっかけになればと思いますけど。
チームに蔓延する当事者意識が未来をつくる。
他人事意識。
これは政治だけでなく、我々のビジネスにおいても重要な課題です。
誰かがやってくれる、自分が頑張っても頑張らなくても何も変わらない、別に会社には何も期待していない、とりあえず自分には関係ない、そんな無関心かつ他人事意識が蔓延している組織に未来なんてあるはずもありません。
だから、スタッフも自分自身の事として本気で置き換えてみることです。
そして、リーダーも本気で意見具申してくることに耳を傾けることです。
何も難しいことなんてありません。
マジで取り組む、それだけです。
一人ひとりが本気で取り組む、それは言い換えると「当事者意識」となるんです。
よく中小企業なんて「トップ一人の実力」で決まってしまうと言われます。
考えてみると、大企業と違ってトップ一人で物事を判断して進めていかないとならない場面ばかりですからね。
だから、ある意味では当たり前の事なのかも知れません。
でも、そこにトップと同じような「当事者意識」を持つスタッフがいたらどうでしょうか。
トップを実務面でサポートする、任せられるスタッフがいたらどうでしょうか。
少なくても役割分担が出来る事によって、トップの判断基準を高めてくれると思います。
これは経営力のアップに繋がりますよね。
経営力のアップなくして、これからの時代なんて生き残ることは出来ないですからね。
その原動力はチームに蔓延する当事者意識だと、そういう事です。
自分がやる、自分が頑張らねば誰が頑張るのか、自分が会社の希望になる、そんな当事者意識が蔓延している組織にこそ、明るい未来がある。
(by マグロちゃん語録)
だからこそ、マジで取り組む、それだけです。
今日もやり切りますよ。
それがコウフ・フィールド株式会社のリーダーの役割ですから。
ではでは。
そうそう、ブログランキング参加中ですから、ぜひ応援クリックもお願いしますね。
今何位だと思います?
以下の画像をポチッと押すだけで分かりますよ(笑)
↓↓↓
あっ、ここスルーしようとしたでしょ!
ダメですよ、ちゃんと押して下さいね(笑)
★マグロちゃんのインスタグラム(フォローしてね)
→ http://instagram.com/kajiki_hidetaka/
このブログではコメントの受け付けはしていませんが、フェイスブック・Xへの同時投稿もしておりますので、そちらでご意見だとか激励のメッセージを頂ければ嬉しいです。
★マグロちゃんのX(フォローしてね)
→ https://x.com/kajikihidetaka
★マグロちゃんのフェイスブック
→ https://www.facebook.com/hidetaka.kajiki
でも、クレームだとか苦情は・・・・ご勘弁くださいネ、だって凹むから(笑)
Let’s enjoy life.by Hidetaka Kajiki
(ニックネーム:マグロちゃん)
マグロちゃん
最新記事 by マグロちゃん (全て見る)
- 「票の行き先」が投票時点の有権者の選択から離れてしまっていいのか? - 2026年2月13日
- 降水量は過去50年で最低!? - 2026年2月12日
- 「それでは皆さま、大きな拍手をお願いします」とは? - 2026年2月11日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
- PREV
- ニックネーム「マグロちゃん」とは!?
- NEXT
- 大相撲に学ぶ「小よく大を制す」という視点。